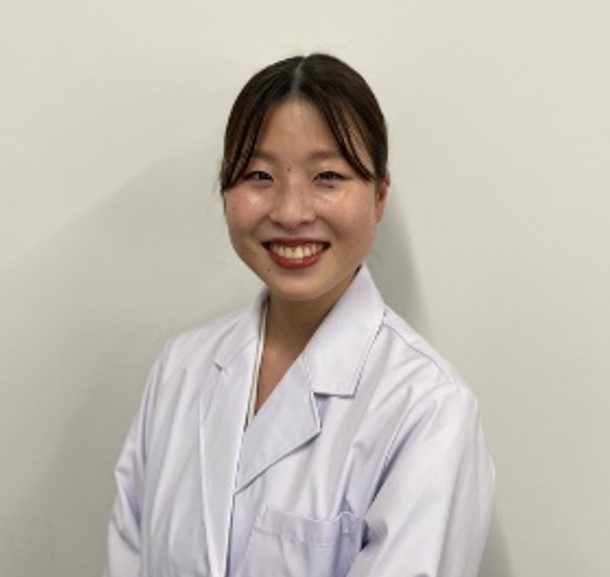2025.10.17
高血圧対策
血糖対策
メタボ対策
健康食
痩せているのに中性脂肪だけ高いのはなぜ?原因と改善の食生活ポイント

見た目は痩せているのに、健康診断で中性脂肪の数値だけが高いと指摘されるそんな経験はありませんか?体型と血液検査の結果が一致しないことに戸惑う方も多いでしょう。実は、痩せていても食習慣や生活リズムによって中性脂肪は上昇しやすく、放置すると動脈硬化などのリスクにつながることがあります。
本記事では、痩せ型なのに中性脂肪が高くなる原因と、今日から始められる食生活の改善ポイントをわかりやすく解説します。
目次
1.痩せているのに中性脂肪が高くなる仕組み

中性脂肪は体内でエネルギー源として蓄えられる脂質の一種です。見た目が痩せていても、糖質やアルコールの摂り過ぎによって肝臓で合成が進み、血中濃度が上昇することがあります。
特に次のような生活習慣が影響します
- 主食中心で、たんぱく質や野菜が不足している
- 夜遅くに食事や飲酒をしている
- 通勤や家事以外でほとんど運動をしていない
このような「痩せているけれど代謝が落ちている状態」では、脂質がエネルギーとして消費されにくく、血液中に中性脂肪が残ってしまいます。見た目では健康そうでも、動脈硬化や脂質異常症などのリスクが進行している可能性があります。定期的な健診と食生活の見直しを行いましょう。
2.中性脂肪が高くなってしまう食習慣と改善のコツ

中性脂肪が高くなる食習慣には、いくつかの典型的なパターンがあります。特に痩せ型の人は「食が細い=栄養バランスが良い」と誤解し、糖質中心や偏った食事になりがちです。
- 白米・パン・麺類など糖質中心の食事
- 甘いお菓子やジュースの摂取が多い
- アルコールを週数回以上飲む
- 果物やスムージーを過剰に摂っている
果物は一見ヘルシーですが、果糖(フルクトース)が多く含まれ、摂り過ぎると中性脂肪の合成を促進する原因になります。特にスムージーやジュースの形で摂ると吸収が早く、血糖値の急上昇につながりやすい点にも注意が必要です。
改善のポイントは「糖質を控えて良質なたんぱく質と脂質をとる」こと。魚や大豆製品、ナッツ、オリーブオイルなどに含まれる不飽和脂肪酸を意識的に摂ることで、脂質代謝が改善されます。中でも青魚に多いDHA(ドコサヘキサエン酸)・EPA(エイコサペンタエン酸)は、血中中性脂肪の合成を抑える働きがあり、動脈硬化の予防にも効果的です。また、野菜や海藻に多く含まれる食物繊維は、余分な脂質を吸着し排出を促すため、食事全体のバランスを整える助けになります。
3.痩せている人の中性脂肪に関するQ&A
「中性脂肪だけ高い」と言われたとき、多くの人が抱く疑問をQ&A形式で解説します。
Q.痩せているのに中性脂肪が高いのは病気ですか?
A.多くの場合は生活習慣が原因ですが、甲状腺機能低下症や脂質代謝異常など、病気が関係していることもあります。一度医師に診ていただくことをおすすめします。特に数値が極端に高い場合や、家族に脂質異常の既往がある場合は早めの受診が安心です。
Q.ダイエットで中性脂肪は下がりますか?
A.極端な食事制限は逆効果になることがあります。栄養バランスを整え、糖質やアルコールを控えながら、魚や大豆製品、野菜中心の食事を意識しましょう。また、有酸素運動(ウォーキング・ジョギング・サイクリングなど)を1回30分、週3〜4回続けると、エネルギー代謝が促進され中性脂肪の分解が進みます。特に朝や食後2時間後の軽い運動は効果的です。
Q.サプリメントで改善できますか?
A.EPA・DHAなどのオメガ3脂肪酸を補うサプリメントは、中性脂肪値を下げる補助として有効な場合があります。ただし、サプリに頼りすぎず、食事と運動の見直しが基本です。魚(サバ、イワシ、サンマなど)を週2~3回取り入れると、自然に必要量を補うことができます。
4.中性脂肪を下げる魚と野菜の和定食レシピ

中性脂肪を下げることを意識した、魚と野菜をたっぷり使う和定食のレシピをご提案します。この定食は、EPA・DHAが豊富な青魚、食物繊維が豊富なきのこや海藻、全粒穀物を組み合わせることで、中性脂肪の低下と血糖値の急上昇を防ぐ効果が期待できます。
献立内容
|
主菜 |
サバの味噌煮 (EPA・DHAが豊富) |
|
副菜 |
きのこのポン酢和え (食物繊維が豊富) |
| 汁物 | わかめと豆腐の味噌汁 (食物繊維・大豆イソフラボン) |
| ご飯 | 玄米または雑穀米 (食物繊維) |
主菜:サバの味噌煮
<材料(2人分)>
|
食材 |
分量 |
|
サバ(切り身) |
2切れ |
|
生姜(薄切り) |
3〜4枚 |
|
水 |
100ml |
|
酒 |
大さじ2 |
|
砂糖 |
小さじ1 |
|
味噌 |
大さじ2 |
|
みりん |
大さじ1 |
<作り方>
1.サバの切り身は軽く水で洗い、ペーパータオルで水気を拭き取ります。皮目に切り込みを入れ、酒(分量外)を少々振っておくと臭みが取れやすくなります。
2.鍋に水、酒、砂糖、生姜の薄切りを入れて中火にかけます。沸騰したらサバの切り身を入れ、アルミホイルなどで落とし蓋をして中火で5分ほど煮ます。
3.味噌とみりんを混ぜておき、煮汁で少し溶いてから鍋に加えます。
4.煮汁をサバにかけながらさらに5〜7分加熱。煮汁にとろみがつき、サバに火が通るまで煮込んだら完成
副菜:きのこのポン酢和え
<材料(2人分)>
|
食材 |
分量 |
|
しめじ |
1/2株 |
|
えのき |
1/2袋 |
|
舞茸 |
1/2株 |
|
ポン酢 |
大さじ2 |
|
ごま油 |
小さじ1/2 |
|
刻みねぎ |
適量 |
<作り方>
1.きのこは石づきを取り、ほぐしておきます。
2.鍋に少量の水を入れ(またはレンジ対応皿にきのこを入れラップをする)、きのこを蒸します(またはレンジ加熱)。きのこがしんなりしたらザルにあけ、水気をよく切ります。
3.ボウルにポン酢とごま油を入れて混ぜ合わせ、粗熱を取ったきのこを加えて和えます。
4.器に盛り付け、刻みねぎを散らしたら完成です。
汁物:わかめと豆腐の味噌汁
<材料(2人分)>
|
食材 |
分量 |
|
だし汁 |
400ml |
|
豆腐(絹or木綿) |
1/4丁 |
|
乾燥わかめ |
大さじ1 |
|
味噌 |
大さじ1〜1.5 (お好みで調整) |
|
長ネギ |
少々 |
<作り方>
1.豆腐は1cm角に切る。乾燥わかめは水で戻すか、そのまま使用する。
2.鍋にだし汁を入れて火にかけ、沸騰したら豆腐とわかめを加える。
3.火を止める直前に味噌を溶き入れる。
4.器に盛り付け、刻みねぎを散らして完成。
ご飯:玄米ご飯
<材料>
|
食材 |
分量 |
|
玄米 |
1合 |
|
水 |
250ml〜300ml(玄米の約1.5倍) |
<作り方>
1.玄米を軽く洗い、ザルに上げて水気を切る。
2.炊飯器の内釜に入れ、規定量の水を加え、最低2〜3時間浸水させる。
3.炊飯器の「玄米モード」で炊飯する。
4.炊き上がったら10〜15分ほど蒸らし、しゃもじで底から軽くほぐして完成。
※より手軽にするため、市販の雑穀米ミックスを白米に混ぜて炊くのもおすすめです。
中性脂肪を下げるためのポイント
ご飯を工夫する
白米ではなく、玄米や雑穀米に替えることで、食物繊維の摂取量が増え食後の血糖値の上昇が緩やかになり、中性脂肪が作られにくくなります。
食べる順番
食物繊維が豊富な副菜や汁物を先に食べ、次に主菜(魚)、最後にご飯を食べることで、より効果的に血糖値の急上昇を防げます。
油の種類
炒め物をする際は、ごま油やオリーブオイルなどの良質な油を少量使うようにしましょう。
砂糖を控える
砂糖の過剰摂取は、体内で中性脂肪に変わりやすく、数値を上昇させる原因となるため煮物などに使う砂糖は少なめにするか、みりんなどの自然な甘味を活かすようにしましょう。
5.中性脂肪改善を無理なく続ける工夫
中性脂肪の改善は「継続」が何より大切です。食生活を無理なく整えるための工夫として、次のようなポイントがあります。
- 1日3食をできるだけ同じ時間にとる
- 夜食や遅い時間の飲酒を避ける
- 糖質の”量”だけでなく”質”を意識し、精製度の低い主食(玄米・雑穀米・全粒粉パンなど)を選ぶ
- 軽い運動を毎日15分以上続ける
白米やパンなど精製された糖質は血糖値を急上昇させやすく、中性脂肪の合成を促す要因となります。主食を雑穀米やオートミールなどに置き換えることで、糖の吸収が穏やかになり、脂質代謝の改善にもつながります。また、ウォーキングやストレッチなどの軽い運動を継続することで、脂質がエネルギーとして消費されやすい体質づくりができます。
忙しい人には、タイヘイファミリーセットの「ヘルシー御膳」がおすすめです。専門医、管理栄養士監修のメニューで、魚や野菜を中心にバランスよく組み合わせた食事が手軽にとれます。中性脂肪対策の第一歩として、食生活の基盤を整えるサポートとして活用してみましょう。
6.まとめ
痩せているのに中性脂肪が高い原因は、見た目ではわからない食習慣や生活リズムの乱れにあることがわかりました。糖質やアルコールの摂り過ぎ、運動不足などが重なると、体重は増えなくても血液中の中性脂肪は上昇してしまいます。
改善の鍵は、糖質を控えめにして良質なたんぱく質と脂質を摂ること。特に青魚に含まれるEPA・DHAは中性脂肪の低下に効果的で、週に2〜3回は魚料理を取り入れたいところです。また、野菜や海藻の食物繊維も余分な脂質の排出を助けてくれます。
生活習慣の改善は一朝一夕にはいきませんが、小さな変化を積み重ねることで必ず成果は現れます。まずは主食を雑穀米に変える、夜遅い食事を控える、毎日15分歩くなど、できることから始めてみることをお勧めします。さらに定期的な健診で数値の変化を確認しながら、健康的な体づくりを目指していきましょう。
-

-
この記事が気に入ったら
いいねしよう!最新記事をお届けします。